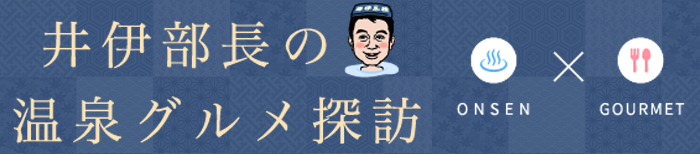福住楼 箱根塔ノ沢温泉
-
文化財の宿として、昔の良さをこのまま残していきたい
初代女将は箱根のシーズンオフ対策の先駆者
福住楼の四代目、澤村社長に福住楼の歴史や建物などについて伺いました。
お話を伺った場所は館内のバー「帰郷」。もともとはビリヤード場だったというバーはクラシカルな雰囲気で、ステンドグラスが印象的です。
福住楼の歴史をひもとくと、売りに出されていた旅館を買い取り、明治23年(1890)に創業。
「初代女将の長谷川まつは料理上手で商売上手。塔之沢の名物女将として、旅館経営に腕をふるっただけでなく、箱根の集客にもつとめました。箱根といえば、かつては湯治のお客さまが多かったのですが、紅葉(もみじ)を宣伝することにより、晩秋から初冬にかけて訪れる人が少なくなる塔ノ沢にお客さまを集めたのです。その宣伝ぶりが猛烈だったため、人からは紅葉狂(もみじきょう)と言われていました」
現在、紅葉シーズンの箱根はたいへんな人出になります。明治時代の紅葉の時期はシーズンオフで、その集客をつとめたのが福住楼の初代女将さんというのは感慨深いですね。
3階建ての建物すべてが国の登録有形文化財に
福住楼は2003年に3階立ての建物すべてが国の登録有形文化財に指定されました。創業から1世紀以上を経て、その建材や建築様式、意匠などが高く評価されたのです。
建築の造り方にも、茶道や華道などに見られる格式の表現形式の「真・行・草(しん・ぎょう・そう)」が用いられています。
「『真・行・草』は書道で言えば、楷書体(かいしょたい)・行書体(ぎょうしょたい)・草書体(そうしょたい)に相当します。『真』の建物で言うと、書院やお寺の本堂などがあり、格式のあるきちんとした造りですね。でも、お客さまはくつろげません。また、『草』ですと、たとえば田舎の茅葺きの家を想像してください。自分の家にいるようでくつろげるのですが、くつろぎすぎて格式が保たれません。その間にバランスを取るために『行』を入れるのです」
福住楼の舞台付きの大広間で言うと、「月の間」は格式を保つために「真」を用いています。一方、舞台側の空間はくつろげるように「草」や「行」を入れているそうです。
また、皇族が逗留した客室も「真」でできているそうです。そうした観点から木造建築を見たことがなかったので、たいへん勉強になりました。
「現在、福住楼の建物はだいぶ古くなってきたので、少しずつ直しています。直し方にもさまざまな方法があり、建物は人間がつくるものですが、建物が人に与える影響もあると思います。基本的に木造の家は手入れをすれば長持ちします。しかし、現在の部屋に風呂やトイレを付けると崩れて壊れてしまいます。変えていかなければいけない部分もありますが、文化財の宿として、保存できるものはそのままにして大切にしていきたいと考えています」