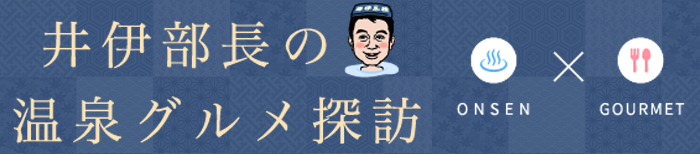ホテル暖香園 伊東温泉
-
料金以上の満足を感じていただく
それが私たちの考え方です
大日本帝国憲法が発布された明治22年。
創業者の別荘を旅館にしたのが暖香園の始まりです。
明治の初め頃の伊東は、鉄道もなくとてもひなびたところでした。ただ、温泉が出ることは知られていて、明治時代の名士達がここに別荘を作ることが多かったようです。
今回インタビューを受けていただいたのは、ホテル暖香園の代表取締役の北岡貴人氏。創業当時から現在に至る暖香園にまつわるとても興味深い話をお伺いすることができました。
「創業者は私から数えて5代前。当時は、丹那トンネルがなく伊東駅どころか熱海駅もなく、東京から伊東には東海道線の国府津(こうづ)で降りて、船で伊東の港に来る以外になかった時代です。
その頃から、伊東には温泉が出ることが知られていて、私の先祖もここに別荘を建てたわけですが、そのお湯がとても良く、ぜひ他の人たちにも入ってもらおうと思い旅館にしたそうです。それがホテル暖香園のはじまりです。
港からまっすぐ続く道の突き当り、現在と同じ場所に旅館を開業したのですが、この辺りは港から近くとても便利だったため、明治の名士達の別荘がたくさん並んでいたそうです。2024年から発行される予定の新しい千円札の顔となる北里柴三郎先生の別荘も近くにあり、また、ホテル暖香園の別館になっている場所は、大日本麦酒(現在のアサヒビールやサッポロビールなどの前身)の社長も務めた馬越恭平氏の別荘でした。」
鉄道すらなかった明治時代。別荘が立ち並ぶこの地で開業した1軒の旅館。明治時代を描いた映画の1シーンのようなイメージが浮かんでくるお話です。そこからどのように発展してきたのか、北岡氏の話は続きます。
「昭和43年には、前の道がそれまでの細い道から広い道路に変わったため、現在の本館を建設しました。以来、毎年改装を行いながら現在に至っています。
というのも、いつ来ても同じだとお客さまに飽きられてしまいますし、時代が移ると旅館の流行りも変わります。従業員も、何もしないでいると「ここにいても先行きが明るくないから」と辞めてしまうことにもなりかねません。だから常に変化を続けているのです。」
その後、ホテル暖香園は120室を擁する大型の宿として伊東の地で確かな基盤を築いていきます。昭和46年には有名な「ダンコーエン・ボウル」もオープン。ボウリングブームの追い風もあり、観光の目玉になるとともに、宿泊客の楽しみも大きく広がりました。

お話を伺う井伊湯種(左)と北岡氏(右)
次に、おもてなしの考え方を伺ってみました。
「ホテル暖香園の考え方は、料理や接待を受けたお客さまが、支払った料金以上の満足を感じていただくことです。うちは料金もそれほど高くないので、高額な旅館とは違う内容で、より多くのお客さまに「泊まって本当によかった」と思っていただけるように心がけています。
例えば、料理一つとってもお客さまのお好みに出来るだけ沿えるようにしています。また、朝食のバイキングもいろいろなものを取り揃え、質にもこだわり、大人も子供も、女性もシニアも、みんなが楽しめる朝食にしています。特に、アジの干物は地元の伊東のものを使うようにしていて、これが美味しいとご好評をいただいています。
他の生産地はほとんどが干物を機械で干していますが、伊東の干物は天日干しが基本です。機械で干したものは中まで乾燥してしまうため、身も乾燥してしまい焼いて食べるときに皮の部分にくっついて剥がしにくくなってしまいます。ところが伊東の干物は、皮の部分がパリッとしていても中は半生状態です。焼いて食べるときに身がふっくらしていてホロホロと崩れ、とても食べやすくて美味しいのが特長です。
従業員の接客についても、現在外国人の従業員が多いため、毎週水曜日に日本語の先生にお願いして、日本語の使い方だけでなく、日本人の習慣や考え方などを教えるようにしています。
逆に、日本人の従業員には、毎週木曜日に英語の勉強をさせています。」
経験豊かな経営者としてのお話を通じて、長い歴史の上にあぐらをかくのではなく、常に変わり続けること、進化し続けることの大切さを学ばせていただきました。
伊東の歴史の一部として存在感を持ち続け、これからさらに未来に向けて力強い歩みを続けていくであろうことを感じました。